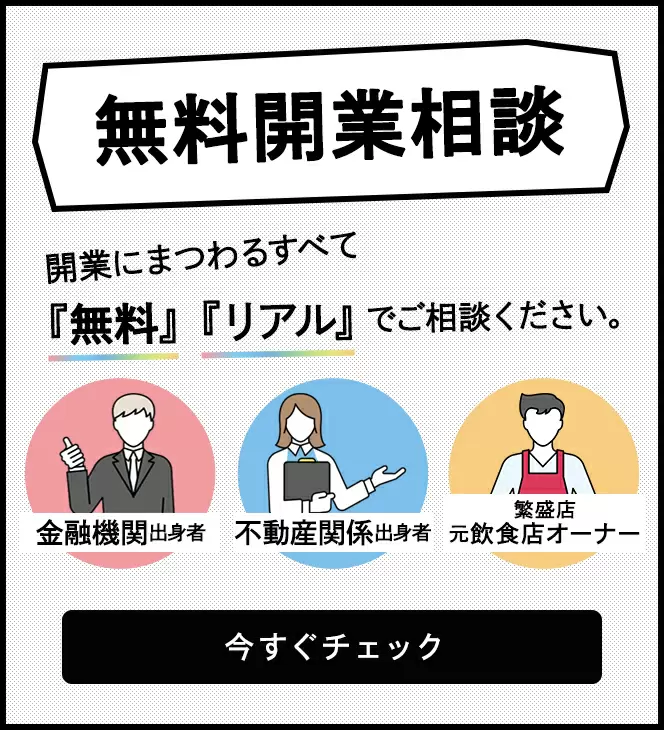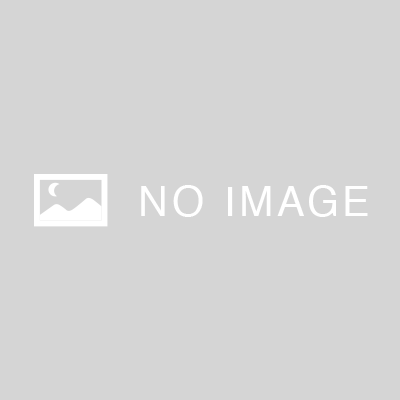目次
1. はじめに:回転率は万能か?という問いから始めよう
「もっと回転率を上げないと、利益が出ない。」
飲食店を経営する多くの人が、一度はそう思ったことがあるはずです。
でも、ちょっと待ってください。
本当に、すべての飲食店に“回転率アップ”は正解なのでしょうか?
もし今、その常識に疑問を感じているなら――この先を読み進めてください。
2. 回転率が生まれた背景とは?
飲食店の売上は、ざっくりこう定義されます。
売上 = 客数 × 客単価
客数は「席数 × 回転数」で増やすことができるので、
「より多くの人を、より早く回す」という思考に行きつくのは自然なことです。
しかし、この前提が成立するのは、すべてのお店で共通とは限らないのです。

3. 回転率至上主義の落とし穴
実際に、ある都内のカフェでは、平均滞在時間を40分に制限するオペレーションに変えたところ、
SNS投稿数が半減し、リピーターも目に見えて減少しました。
「落ち着けなかった」「急かされた」と感じたお客様が、
静かにお店から離れていったのです。
数字に表れにくい“感情の離脱”こそが、最大の機会損失になることもあります。
4. 高滞在型でも売上が伸びるお店の共通点
一方、地方のブックカフェでは真逆の設計がされています。
滞在時間は平均90分。客単価は2,000円以上。
SNSでの投稿は月80件を超え、広告費ゼロで新規流入が続いています。
なぜか?
お客様は「時間を楽しみに来ている」のです。
早く回すのではなく、“長く覚えてもらう”価値が売上を生んでいるのです。

5. 新しい指標「共鳴率」とは?
ここで私たちが提案したいのが、「共鳴率(Resonance Rate)」という考え方。
これは、「お客様が語りたくなる体験」がどれだけ生まれているかを示す独自の指標です。
具体的には…
- 来店後にSNS投稿があったか
- 写真を撮りたくなる仕掛けがあったか
- 接客の言葉が記憶に残ったか
- 再訪したくなるきっかけがあったか
数字では見えない体験が、未来の売上を連れてくるのです。
6. 回転率を“設計”するという考え方
「回転率は上げるか、下げるか」の二択ではありません。
むしろ、
- 昼:高回転設計(ランチセット・制限時間付き)
- 夜:低回転設計(ペアリング体験・空間演出)
といった、“時間帯での使い分け”や“ターゲット層ごとの回転率設計”が鍵です。
✔️設計事例
| 時間帯 | 回転率 | 空間の工夫 | 提供価値 |
|---|---|---|---|
| 平日ランチ | 高め | 時間表示POP/配膳自動化 | スピード・コスパ |
| 土曜ディナー | 低め | 間接照明/BGM設計 | 滞在体験・記憶化 |
| 日曜午後 | 中程度 | Wi-Fi/電源/書籍棚 | 学び・癒し |
「回転率」は、設計するもの。調整するもの。固定概念ではありません。

7. まとめ:あなたの回転率は戦略になっているか?
回転率を上げるべきかどうか――その問いの答えは一つではありません。
重要なのは、「なぜ上げるのか」「誰に対してなのか」「何を犠牲にしているのか」を明確にすること。
回転率は、目的ではなく「変数」です。
戦略に応じて、最適な“バランス”を設計することが、これからの飲食経営には求められています。
✅8. 公式LINEで無料セミナー定期配信中
📥 あなたのお店の“回転率バランス”を見直すきっかけをプレゼントします。
今すぐ、公式LINEを登録して一緒に店舗向上を目指しましょう!