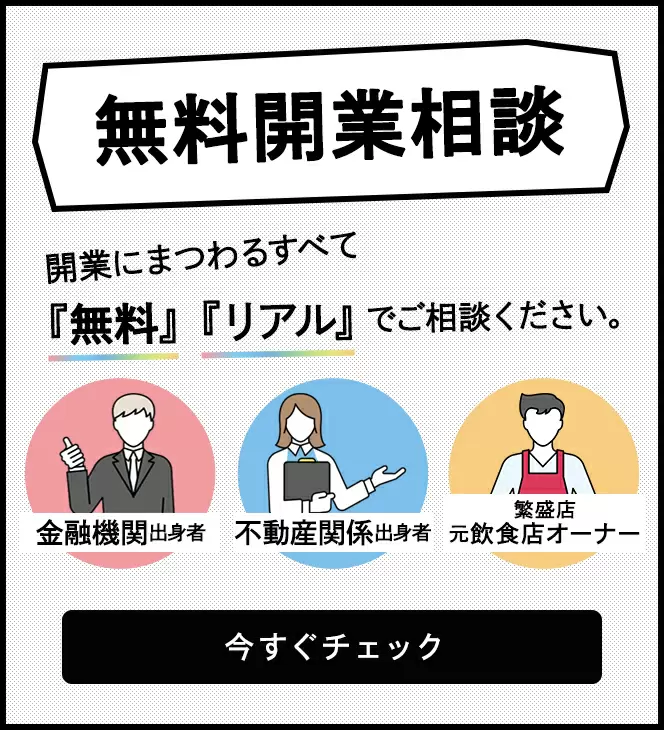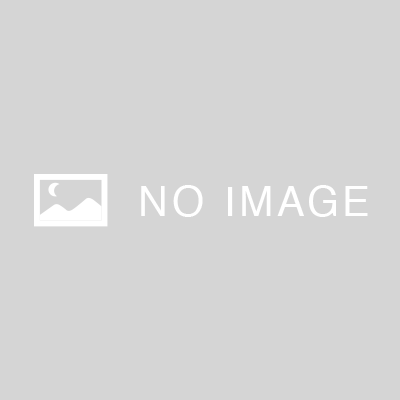目次
1. 営業許可と食品衛生法の関係
飲食店を開業するには、営業許可の取得が必須です。そしてその前提となるのが「食品衛生法の遵守」。
つまり、この法律を知らない状態では開業すらできないのです。
実例: 東京都内で準備を進めていたオーナーが、食品衛生責任者の講習を後回しにしたため、営業許可が降りず開店が2か月遅れました。開店延期による家賃・人件費の損失は数十万円にのぼりました。
2. 経営者が責任主体となる理由
士業や行政書士が申請書を手伝ってくれることはあっても、日々の運営判断を代行してくれるわけではありません。
「この食材は廃棄すべきか?」「異物混入時にどう対応するか?」といった現場の決断は、最終的に経営者に委ねられます。

3. 現場判断を誤るとどうなる?
温度管理の基準を知らずに保存した結果、食中毒を招いてしまうケースは少なくありません。たとえ軽度でも、保健所からの営業停止命令が下れば売上はゼロになります。
例: 某居酒屋チェーンでは冷蔵温度の記録漏れが原因で営業停止。1週間で数百万円規模の売上を失ったと報告されています。
4. SNS炎上リスクは一瞬で拡散する
現代は口コミの時代です。衛生違反や異物混入は、来店客のSNS投稿で一気に拡散されます。
広告費を投じても「不衛生な店」という評判がつけば、検索結果や口コミはマイナス評価で埋まり、長期的な集客力を失います。

5. 法律理解を“攻めの武器”に変える
「食品衛生法を守る」ことは義務ですが、それを前向きに活用すれば「強力な武器」にもなります。
「うちは食品衛生基準を徹底して管理しています」と発信するだけで、他店との差別化が可能になります。
実例: 衛生管理体制を公式サイトに明記したあるレストランでは、「安心して子どもを連れて行ける」と口コミ評価が増え、来店数が前年比120%まで伸びました。
6. 安心・安全がブランドになる
「この店なら安心して食べられる」と感じてもらえることこそ、最大のリピーター獲得戦略です。
味や価格だけでなく、安心・安全も顧客が店を選ぶ大きな基準となっています。

7. 学びの第一歩と行動指針
食品衛生法を理解することは「リスク回避」だけでなく「経営の基盤」。
最初の一歩は、食品衛生責任者の講習を受けること。さらに厚生労働省や自治体が発行する公式マニュアルを確認し、自店用にアレンジしたルールブックを作成するのが効果的です。
8. まとめと次のステップ
食品衛生法を知らないまま開業するのは、法的にも経営的にも極めて危険です。
一方で、正しく理解すれば「安心・安全」という最大のブランド資産に変えることができます。
👇今すぐ「公式LINE」にご登録いただき無料zoom面談を受けませんか?
開業準備の抜け漏れを防ぎ、あなたの飲食店を安心・安全な経営へ導けます。