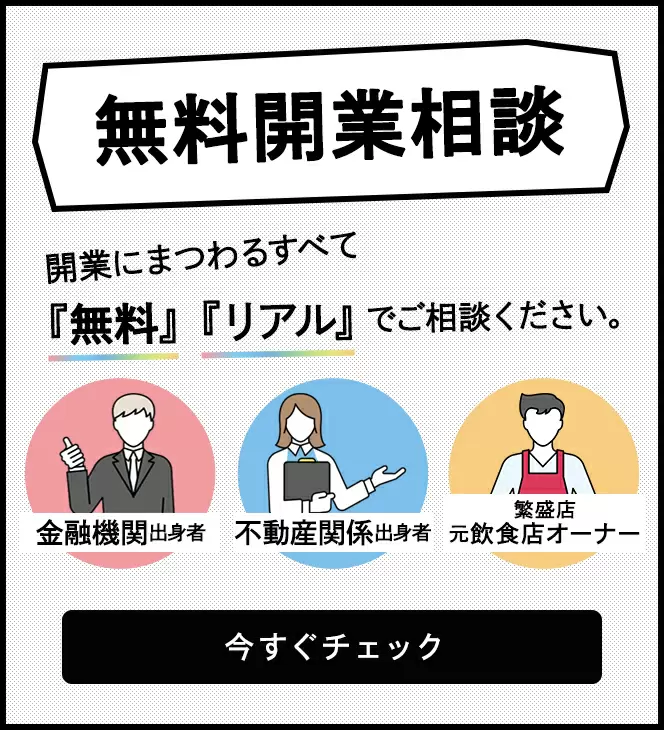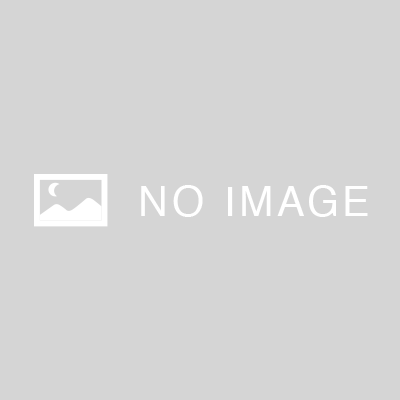目次
1. FL比率とは?──知っているようで見落としがちな本質
飲食業界でよく聞く「FL比率」という言葉。
これはF=Food(原材料費)とL=Labor(人件費)を足し合わせ、それを売上で割った比率のことを指します。
FL比率 =(原価 + 人件費) ÷ 売上
一般的には60%以下が健全と言われ、70%を超えると「危険」とされがちですが…
果たしてこの数字、ただ“下げれば良い”のでしょうか?
2. なぜFL比率が経営判断の軸になりやすいのか
FL比率は、一見とても分かりやすい指標です。
なにしろ「材料と人件費を抑えれば利益が出る」と思わせてくれるから。
でも実際の現場では、こんな声をよく聞きます。
- 「看板メニューが高原価すぎて悩んでいる」
- 「人手不足で人件費が膨らむのを止められない」
- 「FLは良いのに、なぜかお金が残らない」
そう。数字が“良い”からといって、経営が“うまくいっている”とは限らないのです。

3. FLを下げればいい、という大きな誤解
FL比率を下げようとして、真っ先に削られがちなのが、
- 食材の質
- 人員配置
つまり、お客様に直接価値を届ける部分です。
けれど、それによって
- 味が落ちる
- サービスの質が下がる
- リピート率が低下する
といった事態が起きれば、本末転倒ですよね。
4. 数字ではなく“構造”を読む──次元別の思考アプローチ
FL比率は「2次元の数字」です。
でも、経営はそれ以上に複雑です。
| 次元 | 視点 | キーになる考え方 |
|---|---|---|
| 2次元 | コスト | FLの“数値”だけを見る |
| 3次元 | 売上構造 | 客単価×客数×回転率 |
| 4次元 | 顧客価値 | “高原価”が生む感動・満足 |
| 5次元 | 経営哲学 | あなたのお店の“価値観”が反映された数値 |
FL比率はただの目安であって、経営のゴールではないという視点が必要です。

5. 【具体例①】FL比率68%でも利益を出す店の正体
都心のあるイタリアンでは、FL比率が68%。
一見「高すぎる」と思えますが、実は月商1,200万円以上を安定して記録しています。
その理由は:
- 高単価コースで満足度を最大化
- ドリンクで粗利を確保
- サービスに人件費をかけ、リピート率を強化
つまり、FL比率が高いのではなく、意図的にそうしているのです。
それが、彼らの戦略。
6. 【具体例②】FL比率55%でも赤字になる店の真因
一方で、地方にある定食屋。FL比率は55%。
教科書的には“健全”ですが、実際は赤字続き。
理由を見てみると:
- 客単価が1,000円以下
- 席数が少なく、回転率も1回以下
- 滞在時間が長く、オペレーションも非効率
つまり、売上の構造が弱いのです。
FL比率だけでは見抜けない問題があることがわかります。

7. FL比率を“結果”ではなく“戦略”として活かすために
FL比率は、売上・商品・人材・ブランド…すべての構造の“結果”として出てくる数字です。
だからこそ、次のように捉えるべきです。
- FLが高い → 高原価メニューで差別化できている?
- 人件費が高い → 接客でブランド価値をつくれている?
- FLが低すぎる → お客様への価値提供が減っていない?
**「数字の背後にある構造」**を読み解くことで、経営判断の質が格段に変わります。
🎯 終わりに
数字を見る力とは、表面だけを“比率”で追うことではありません。
それがなぜそうなっているのか、経営の“背景”を構造的に見抜く力こそが、数字を味方につける鍵です。
あなたのFL比率は、「削るための指標」ですか?
それとも「磨くための戦略」ですか?
本質を見失わず、利益と価値を両立できる経営を、ここから一緒につくっていきましょう。
【公式LINE登録無料特典あり🎁】
数字に振り回されるのではなく、数字を**“読解”して、戦略に変える**思考力を身につけたい方へ。
📩 今だけ公式LINEでの無料定期セミナー配信中!
📲 【今すぐ公式LINEに登録】して、あなたのお店の経営を“戦略型”に変えていきましょう👇