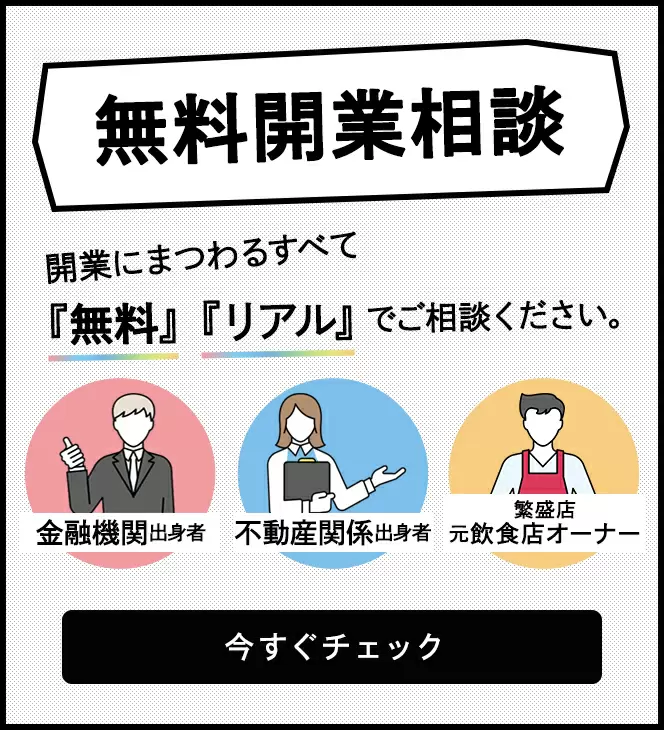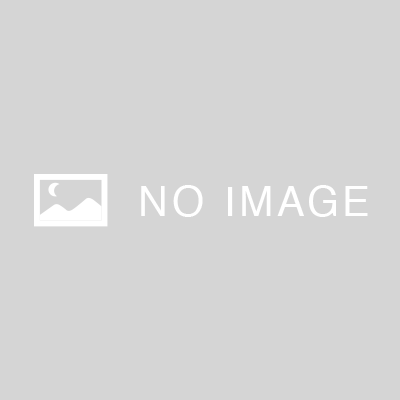目次
1. はじめに:なぜ「名前」に違いを感じるのか?
「バルって気軽な感じだけど、ダイニングってちょっとおしゃれな印象」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実はこれ、あなたの感覚が間違っているわけではありません。
でも、その“違い”には制度的な格差も定義も存在していません。
それなのに、私たちは無意識に名前から「空気」や「値段」まで判断してしまう。
この記事では、その仕組みと、飲食店経営におけるネーミングの本質的な役割についてお話ししていきます。
2. 名前で差がつく?お客様の“印象”はどこで決まるのか
たとえば「バル」と「ダイニングレストラン」。
この2つを並べたとき、どちらに“高級感”を覚えるでしょうか?
ほとんどの人が、後者によりフォーマルで上質な印象を持つはずです。
しかしこの違いは、価格や料理の中身ではなく、名前がもたらす期待感の違いにすぎません。
言葉には、意味だけでなく「連想させる空気」があります。
これを“心理的ヒエラルキー”と呼びます。

3. 「言葉が体験を決める」5次元の関係性
では、どうして名前がそんなに強い印象を左右するのか?
それを理解するには、次の5つの要素の交差点として捉えるとわかりやすいです。
| 次元 | 内容 |
|---|---|
| ① 言葉そのもの(語感・語源) | 例:「バル=スペイン」「ダイニング=英語で食卓」 |
| ② 空間(内装・席間・照明) | 視覚情報と名前が一致すると“納得感”が生まれる |
| ③ 価格(期待値との整合) | 安いのに「レストラン」と言ってると違和感になる |
| ④ 文化的背景(輸入・翻訳のズレ) | 言葉の持つ国別のニュアンスや変化 |
| ⑤ メディア・検索(SEO・SNS) | 店名はGoogle・インスタでの表示にも影響する |
たとえば「〇〇バル」という名前なのに内装が高級ホテル並だと、逆に落ち着かない。
お客様の頭の中で「名前」と「現場の体験」が一致していないからです。
4. 実際の店舗事例:成功と失敗、その分かれ目
✅ 成功した事例:ネオ和バル → 客単価+900円
東京都内のある店舗では「和バル〇〇」という名前で営業していましたが、
価格や提供スタイルが“やや上質”になってきたことから「ネオダイニング〇〇」に変更。
結果として:
- 客層が30〜50代の女性中心に変化
- 価格の違和感が解消され、客単価が+900円に上昇
- 「雰囲気が名前と合っていて心地よい」というレビューが増加
❌ 失敗した事例:レストランの誤解で客離れ
一方、地方の洋食店では「レストラン」と名乗ったことで
「高そう」「記念日用っぽい」と感じられ、家族連れの来店数が大幅に減少。
価格・提供内容は以前と変わらないにも関わらず、名前だけで客層が変化してしまいました。

5. あなたの店は大丈夫?名前とブランドの“ズレ”チェック
以下の質問に当てはまるものはありませんか?
- 来てほしいお客様と、実際の客層にズレがある
- 店名の印象と内装・サービスの雰囲気が噛み合っていない
- GoogleやSNSで「なんのお店か」伝わりにくい
- 価格のわりに“軽く見られる”/“重く見られる”ことがある
もし1つでも該当するなら、ネーミングの見直しは有効な施策です。
6. 今日から使える!ネーミング改善の3つの具体策
① ターゲットを再定義する
誰に来てほしいかを、年齢・性別・ライフスタイルまで明確に言語化。
② 名前に補助語をつける
例:「バル」→「ナチュラルバル」「おばんざいバル」など。
呼び名だけで“料理ジャンル”や“空気感”が伝わる。
③ 空間と名前の統一感を見直す
もし名前が“カジュアル”なら、あえて照明を少し明るくする、BGMを軽快にするなど、空間の演出を調整。

7. まとめ:お店の未来は、名前から変わる
名前は単なる「名札」ではありません。
それは、お客様にとって最初のブランド体験であり、信頼や満足度に直結する“入口”です。
逆に言えば、「今の名前」が未来のチャンスを逃している可能性もあるということ。
あなたのお店が、本当に届けたい価値に合った名前になっているか──
いま一度、見つめ直してみませんか?
🎁【LINE登録無料特典】
「とはいえ、何がズレてるかなんて自分ではわからない…」
そんな方のために、飲食専門の視点であなたのお店の名前とコンセプトのズレをお教えいたします!
LINE登録者様限定で無料セミナー定期配信中です。